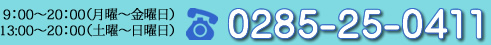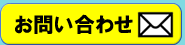相続に関する基礎知識
◆相続する人(相続人)
相続する人とは、故人から財産を引き継ぐ人で、法律で決められた人です。
法律的には、「相続人」と呼びます。参考までに故人は「被相続人」です。
初めて、相続関連の本を読む方は、混乱するかもしれません。
さて、相続人ですが、配偶者(妻もしくは夫)は常に相続人になります。
しかし、内縁関係(事実上は婚姻生活をしているが戸籍上は入籍されていない状態)では、50年以上一緒に暮らしたからといっても、相続する権利はありません。
血族は、下記の通り順位が決まっております。すなわち第1順位の人が既に亡くなっていたり、相続を放棄した場合に第2順位、次に第3順位の人へと移っていきます。
ただ、第1順位の子供が相続するときに既に亡くなっていても、その子、被相続人(故人)からすれば孫が存在していれば、第2順位の父母に相続権は移らず、代襲相続といって孫が相続します。
第1順位 被相続人の子(子が死亡している場合は孫、孫の次はひ孫、ずっと続く)
第2順位 被相続人の直系尊属(被相続人の父・母、配偶者の両親は除かれる)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は兄弟姉妹の子、すなわち被相続人の甥・姪)
◆相続割合(財産分け・法定相続分)
民法によって規定されている相続割合を、法定相続分と言います。
ただ、故人(被相続人)が遺言により、個々の相続財産を誰に引き継がせるか指定した場合や割合を指定した場合は、その遺言が優先されます。
法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となります。
| 相続人 | 法定相続分 | |
| 配偶者のみ | 全部 | |
| 第1順位 | 配偶者と子(孫) | 配偶者:1/2
子:1/2(複数の場合均等割) |
| 子(孫)のみ(配偶者なし) | 全部(複数の場合均等割) | |
| 第2順位 | 配偶者と直系尊属(父・母) | 配偶者:2/3
直系尊属:1/3(複数の場合均等割) |
| 直系尊属(父・母)のみ | 全部(複数の場合均等割) | |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹(甥・姪) | 配偶者:3/4
兄弟姉妹1/4(複数の場合均等割 |
| 兄弟姉妹(甥・姪)のみ | 全部(複数の場合均等割) | |
*養子縁組をした場合は、実子と同じ相続分になります。
*非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)の法定相続分は嫡出子(婚姻している夫婦から生まれた子)の1/2になります。
◆遺贈
遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することです。
たとえば、妻に先立たれ、同居していた長男も亡くなってしまった後、長男の嫁が身の回りの面倒を見てくれているとケースです。
このままでは、長男には子供がなく、嫁には相続の権利がないことから、別居している次男にすべて財産が相続されてしまいます。次男がこの家まで相続してしまうと、長男の嫁は住むところまで失ってしまう可能性があります。この様なときに、遺言書で簡単に財産を長男の嫁に遺贈することができます。
遺贈は、もらう側の意思とは無関係にあげる方の一方的な遺言により生じます。よって、もらう側は、受け取ることを拒否することもできます。
遺贈は遺言者の単独行為ですので、この点で両者の意思が合致している贈与契約とは異なります。
◆遺留分
被相続人(遺言作成者)が、法定相続人以外の特定の人に全財産を贈与するという遺言状を作成することもできます。
しかし、奥さんも子供もいるのに「愛人に全財産を相続する」という遺言により、自分が一銭も貰えないとしたらどうしますか?
大丈夫、あなたには「遺留分」があります。遺族の生活を保障するという趣旨の、一定の割合で相続財産を受け取れる定めが「遺留分」です。
あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、相続人の生活保証ために遺産の一定割合を保証する制度です。
これは、相続人間であまりにも偏った相続の割合を遺言で指定されたときも、主張できます。
遺留分の権利者は、兄弟姉妹以外の相続人になります。子の代襲者(孫)にも遺留分はあります。
しかし、遺留分は権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことはできません。
遺留分が侵害されているときは、法定相続人は自分の遺留分を確保するために、遺留分減殺請求をして、取り戻すことができます。
この意思表示は、内容証明郵便などで意思表示をすればよく、裁判で行使することを要しません。
遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使はできません。
|
法定相続人 |
遺留分 |
|||
|
配偶者と子 |
配偶者 |
1/4 |
子 |
1/4 |
|
配偶者と直系尊属 |
1/3 |
直系尊属 |
1/6 |
|
|
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
兄弟姉妹 |
なし |
|
◆特別受益と寄与分
相続人の中に、被相続人(故人)から生前贈与や遺贈等の特別の利益を受けていた者がいる場合に、遺産を単純に法定相続分どおりに分けると、贈与や利益を受けた者と受けていない者の間で不公平が生じます。これを是正・調整しようとするのが、特別受益の制度です。
このような場合、不公平とならないように、特別受益となる生前贈与・遺贈があった場合には、特別受益を受けた者の 相続分から贈与・遺贈の額が引かれます。これが、特別受益の持ち戻しです。
生前贈与や遺贈の持ち戻し分を遺産の総額にこれらのも加え、生前贈与や遺贈を受けた相続人はその目的を問わず、その分を相続したものとして計算し、遺産分割をする必要があります。
例えば、相続人が故人の奥様と子供2人で、相続財産が5000万円であっても、その子供のうちの一人がマンション購入資金として1000万円を生前にもらっていたときは、その1000万円をもち戻しし、総相続財産は6000万円になります。
総相続財産 = 5000万円 + 1000万円(持ち戻し額) = 6000万円
配偶者(妻)法定相続分(1/2) 3000万円
子A 法定相続分(1/4) 1500万円(生前贈与で既に1000万円もらっているので差額の500万円)
子B 法定相続分(1/4) 1500万円
これに対して、相続人のうちの特定の者だけが相続開始前に被相続人(故人)の財産の形成や維持に貢献をしていたという場合、不公平とならないように、これらの貢献分を考慮し、その相続人の相続分に一定の加算をする制度が寄与分です。
寄与分は、あくまで特別の貢献をしたと認められる場合に限られ、たとえば親族間には一般に扶養の義務がありますので、通常の扶養の範囲内の事柄は寄与分とはなりません。
なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。
◆遺言とその役割
遺言とは、生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者が亡くなられた後にその意思を実現させるための制度です。
法律に反しない範囲内において財産の自由な処分、特に財産の全部もしくは個々の財産を誰が受け継ぐかについて、被相続人(遺言作成者)の意思を反映させることができます。
一方で、民法は遺言に厳格な要件や方式を定めており、それに則っていないものは無効としています。
ⅰ.遺言書があったなら・・・・、後から悔やめません
遺言や相続の問題はとても身近な問題でありながら、ほとんどの方が正しい知識をもっていません。正しい知識が無いがゆえに、残されたご家族が相続による争いに巻き込まれ、悲しい想いをするケースが目立ちます。
相続による争いの原因の大半は、適切な遺言が無かったことにあります。
つまり、適切な遺言が残されていれば、ほとんどのケース、相続による争い・家族関係の崩壊は防げたのです
相続人間の争いごとを未然に防ぐことが、遺言書の大きな目的の1つです。
ⅱ.遺言書作成のメリット
遺言書がない場合、遺産はいったん法定相続人全員の共有となり、その上で遺産をどのように分割するかを相続人間で協議することになります。
相続人それぞれの思惑や欲が衝突し、この遺産分割協議がスムーズにまとまらず、裁判所にゆだねるケースも少なくありません。
このような事態を防ぐために、十分に考慮した上で、誰にどのように財産を相続させるかを明確にした遺言書をあらかじめ作成しておくことが必要です。
遺言に遺産分割方法が指定されている場合は、それに従うことになり、相続人の間で遺産分割協議をする必要はありません。
さらに、遺言書は相続争いの防止だけではなく、残された家族の愛情や感謝の気持ちを伝える大事な手段です。
◆遺言の種類
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。特別方式は、普通方式ができないような特別な事情がある場合(病気やけがで死亡の危機が迫っているような場合など)の特別の様式でごく稀ですので、ここでは普通方式について説明します。
普通方式には、次の3種類があり、それぞれ長所と短所があります。
|
種 類 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
|
概 要 |
自分一人だけで最初から最後まで手書きで作成する遺言 |
公証役場にて、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公正証書にする遺言 |
存在は明確にしつつも、内容は秘密にできる遺言 |
|
作成方法 |
|
印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本等の書類が必要 |
本文は代筆でもワープロでも構わないが、署名だけは自筆。 署名印と同印で封印。 住所・氏名と自己の遺言である旨を申述。 公証人が日付と本人の遺言であることを記載 |
|
場 所 |
自由 |
公証役場 公証人に出張してもらうことも可能 |
公証役場 |
|
証 人 |
不要 |
2人以上 |
2人以上 |
|
署名捺印 |
本人 |
本人、公証人、証人 |
本人、公証人、証人 |
|
家庭裁判所の検認* |
必要 |
不要 |
必要 |
|
メリット |
いつでもどこでも作成できる。 遺言内容や遺言の存在を秘密にできる。 |
検認手続き不要。 |
偽造のおそれが僅少。 |
|
デメリット |
検認手続きが必要。 |
遺言の存在と内容を秘密にできない可能性がある。 信頼できる証人を依頼しなければならない。 |
手続きが面倒。 公証人の手数料がかかる。 紛失・隠匿のおそれ有り。
検認手続きが必要。 |
*遺言書の検認手続きとは
被相続人等関係者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。
検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。
◆遺言でできること
遺言は、一生涯で残した財産を次の世代に譲り渡す行為で、その内容は特に制限はありません。
しかし、法律的には遺言の対象にできる事項について定められています。これ以外の事項については法律上の効力はありませんが、感謝の気持ちや「家族仲良く助け合って欲しい」など、残された家族への想いを盛込むことにより、遺言者の意思や心情を伝えることもできます。
遺言事項は大きく分けて「身分に関すること」「財産の処分に関すること」「相続に関すること」の3つに分けられます。
①身分に関すること
・子の認知
・未成年者の後見人、後見監督人の指定、等
②財産の処分に関すること
・遺贈
・寄付、等
③相続に関すること
・相続分の指定
・遺産分割禁止(最長5年)
・相続廃除またはその取消
・遺言執行者の指定、等
◆相続排除
相続排除とは、相続人の持っている相続権を剥奪する制度です。
本来であれば、相続の資格のある人は、何らの事情がなくても故人と一定の身分関係があれば、当然に相続人になります。
しかし、例外として故人が 生前に相続廃除の申立てを家庭裁判所に行い、その申立てが認められた場合や遺言で廃除の意思表示を行い遺言執行者が遺言に従い廃除を申立て、申立てが認められた場合には相続廃除となり、相続人としての地位を失い相続することはできなくなることがあります。
ただし、この場合も、代襲相続は認められています。
民法において以下の相続廃除が認められる要件が列挙されています。
a. 被相続人に対する虐待
b. 被相続人に対する重大な侮辱
c. その他の著しい非行
廃除される者は遺留分を有する推定相続人とされており、兄弟姉妹以外の相続人が廃除の対象となります。
被相続人が後日、廃除手続によりの相続権を剥奪したのち、非行が改められたり反省の色が見受けられるなどの事情により、廃除を取り消したい場合は、相続排除の取消しができます。これは、いつでも何らの理由がなくても、遺言でもできます。
◆相続欠格
相続欠格とは、被相続人の意思で行われる相続廃除の場合と異なり、一定の事由がある場合に相続権を自動的に喪失することをいいます。
a. 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
b. 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
c. 詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者
d. 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者
e. 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続欠格の場合、被相続人(故人)が許しても相続人たる権利を取り戻す事はできません。
以上の対象となった欠格者の子供でも、欠格者に代わって相続人となること(代襲相続)が許されています。
◆遺言の撤回・変更
遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度ですから、遺言者の意思であれば書いた後で、いつでも自由に撤回・変更をすることができます。
ただし、遺言書の撤回・変更をするには、注意が必要です。
①自筆証書遺言
遺言書を破棄するだけで撤回したことになります。
内容を変更するには、法律で定められた加除訂正の方法によって原文に手を入れることができます。
②公正証書遺言
撤回する場合は、公証役場で撤回の公正証書を作成、もしくは新たに撤回する旨の遺言書を作成します。
新しい遺言書は、自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも秘密証書遺言でも構いません。
訂正の場合は、公証役場にて訂正を申し出るか、新たに変更や撤回部分を記した自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言を作成します。
③秘密証書遺言
自筆証書遺言と同様に、遺言書を破棄するだけで撤回したことになります。
変更・訂正について、秘密証書遺言は公証人が認めて封印したものなので、遺言者であっても開封することができません。新たに変更や撤回部分を記した自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言を作成します。
*遺言書が2通あるとき
遺言書が複数ある場合は、最も新たしい日付のものが有効とされています。
日付の新しい遺言に、前の遺言の内容と抵触する箇所がある場合は、その部分だけ新しい遺言が有効になり、前の遺言の残りの部分もそのまま有効になります。
◆遺言の執行
遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことですが、場合によっては、相続人間で感情の対立が生じたり、もめたりして、スムーズに事が運ばないことがあります。
もめなくても、手続きに法律知識が必要であったり、時間的な問題等で遺言を執行することが難しいケースもあろうかと思います。
そこで、被相続人(故人)が希望したとおりの相続が行われ、遺産分割等、様々な手続きをスムーズに実行するため、被相続人は遺言により、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者の指定は、遺言でしかできません。
遺言執行者とは、簡単に分かりやすく言うと、被相続人(故人)の代理人です。
遺言によって遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は遺言を執行するためのいっさいの権利と義務を持ち、相続人が遺言執行者を無視して勝手に遺産を処分することは許されません。
◆相続手続きの流れ
|
相続の開始 |
|
遺言状の有無 |
|
遺言状有 |
|
遺言状無 |
|
公正証書遺言 |
|
自筆証書・秘密証書遺言 |
|
遺言書の検認請求 |
|
遺言書の開封 |
|
相続人の確定 |
|
相続財産の確認 |
|
遺産分割協議 |
|
遺言指定通りに分割 |
|
相続放棄 |
|
限定承認 |
|
指定以外の財産 |
|
遺産分割 |
|
裁判所にて調停・審判 |
◆相続人の確定
遺産分割協議を始める前に、「誰が法定相続人か」を確定しなければなりません。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければいけないもので、一人でも欠いた遺産分割協議は無効となるからです。
相続人を確定するためには戸籍謄本を取り寄せ、被相続人(故人)の出生から死亡まで途切れなく繋がったすべての戸籍書類を調査・確認します。戸籍が不足しているようであれば、どこから転籍してきたかを調べ、転出元の本籍地に戸籍を請求します。
さらに,相続資格のある人が現在も生存しているかどうかも相続人全員の戸籍謄本などにより、確認しなければなりません。
戸籍謄本を確認していく上で被相続人が生前に子を認知していたり、養子縁組をしていることなどが発覚する可能性があり、この場合には法定相続人や法定相続分が変わってくる場合があります。
◆相続の放棄・限定承認
相続人は被相続人(故人)の遺産の相続を放棄することができます。
たとえば、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、そのまま全てを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならず、借金で苦しむことになります。
そこで民法は、相続人に3つの選択肢の中から自由に選べるようにしました。
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
農地を細分化すると農業経営が不可能になってしまうことから農業を引き継ぐ者にすべて相続させ、他の者は相続放棄するケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続をするとなっても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということもあります。被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、プラスの財産が残っているのであれば、プラス財産の分だけ相続する制度が限定承認です。
逆に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、借金を背負うことになるため、相続はしません。
相続人が複数存在する場合には、相続人全員が限定承認を選択しなければなりません。
なお、3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は、単純承認とみなされます。
◆遺産分割協議
遺産相続において遺言が無いときは、相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、相続人のうち誰か参加していない人がいるとその協議は無効になります。
相続人全員の意見が一致すれば、法定相続に従う必要も無く、どのようにでも自由に分割できます。
協議がまとまったら、通常は遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をして、各自保有します。
この遺産分割協議書には通常相続人全員の実印と印鑑証明書を添付します。
◆相続税
相続税とは、被相続人(故人)の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律で定められていますので、遺産分割がまとまらないので相続税が払えないといった、各自の事情は考慮されません。
この期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することとなります。
◆相続登記
相続が発生したときに被相続人(故人)が所有していた建物や土地などの所有権は、相続人へ移転します。
相続登記とは、その不動産の名義変更手続きのことをいいます。
その不動産を管轄する法務局へ申請しますが、期限はなくいつでもできます。
ただし、放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、後々手続きが面倒になることもあります。